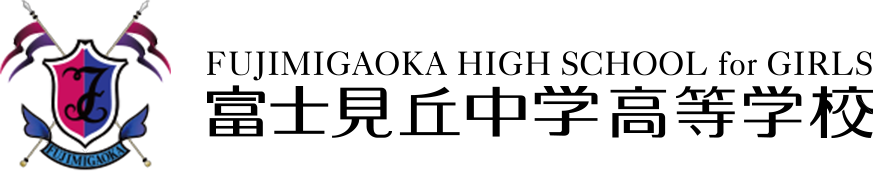生徒全員の意見や考えを共有し、対話をしながら授業を進めていったり、
各自で課題について調べて発表したり。生徒の能動的な授業参加を促しています。
ロイロノートスクールとは?
教員と生徒間の双方向のコミュニケーションを円滑にする授業支援アプリ
英語科 │ 田中先生
ICTを駆使した学びが4技能を伸ばす

Online Speakingの導入やパワーポイントを用いたプレゼンテーションなど、全員がノートパソコンを所持することで授業内容は進化を遂げてきました。近年では音読練習の様子を録音し、オンライン上でのデータ提出を宿題にするなど、英語学習におけるパソコンの用途はますます多岐に渡っています。録音した音声を教員が聴き、一人ひとりにフィードバックしたり、エッセイや英語日記の添削例を授業中に電子モニターで共有するなど、学びの可能性を広げるパソコンの存在は、富士見丘生の英語力の底上げに大きく貢献しています。

ロイロノートによる英作文の課題添削

オンラインで提出された音読のフィードバック例
数学科 │ 志水先生
“好き”から“得意”へ “苦手”から“できるかも!”へ

数学は、1つ1つをきちんと理解していくことが重要です。何をどう考えたのか、わかることとわからないことは何かを明確にすることで力がついていきます。その際、必要に応じてICTを活用し、事象の様子を視覚的に捉えることで、理解を深めていきます。また、中2からはレベル別でのクラス編成を行い、それぞれの習熟度や理解度にあわせてきめ細かく授業を行っています。少しずつそれぞれの「わかる」「できた」といった体験を積み重ねることが、確実な数学力を磨いていくことにつながっています。

回転移動について、geogebraを使った授業の例
国語科 │ 斉藤先生
多くの価値観を共有。
比較し、多様な視点を身につける

国語の授業では、自分の意見をクラスメイトと共有するためにICT、特にロイロノートを活用しています。評論文のみならず、小説や古典文学の解釈についても様々な価値観を互いに比較することができるため、自らの思考を深めることが可能です。文学史や作品の歴史的背景を調べる作業はもちろんのこと、文章理解につなげるための映像資料の確認など中1から高校生までICTを幅広く利用し、数年間かけて多様な視点を持つことができるようになります。

俳句をグループごとに鑑賞し、意見をロイロノートで共有する
理科 │ 林先生
なぜ?なに!を大切にして
「発見力・解決力・発信力」を伸ばす

身近なところにある科学的な事象から理科の楽しさや多面的な思考を養うことを大事にしています。実験実習にじっくりと取り組めるよう各学年共通して2時限続きの授業時間を設定しています。また生徒一人一人が持つPCを活用して、実験実習の目的・方法・結果・考察・感想など一連のまとめと、それをもとにしたグループディスカッション・プレゼンテーションを行い、問題の「発見と解決」、自身の考えを他者へ伝える「情報発信」など主体性を育てる場を提供します。

実験の説明もロイロノートで
TOPICS
理科の取り組み
中1理科「液体窒素を用いた実験」
気体の状態変化と窒素の性質を学ぶため、液体窒素に指を入れたり、火を消したり、花を凍らせたりと、生徒は初めて見て触る液体窒素に終始興奮気味でした。この実験を通して、物質の状態変化を目で見て深い理解ができました。
理科実験では教員が2人ついて安全に配慮したチーム・ティーチングを行い、生徒は体験を通して知識を深めています。
中 1「理科実験」年間の取り組み例
単元 |
実験内容 |
動物の特徴と分類 |
魚類の解剖(マアジ) |
語る大地 |
堆積岩の観察 |
物質のすがたとその変化 |
液体窒素を用いた低温の実験 |
光による現象 |
凸レンズによる像の観察 |

社会科 │ 藤本先生
知る楽しさと自らの探究を表現する授業

全学年でアクティブラーニング形式の授業を展開しています。テーマ学習に際しては「ロイロノート」を使用して、個々人の意見をモニター上に投影しながら話し合いを行います。お互いの批評を通してまとめ上げた学習の成果は、パワーポイントを使ってプレゼンテーションを行います。中1で地理、中2~中3にかけて歴史、中3で公民を学びながら、単なる暗記ではなく知ることの楽しさと自らの探究を表現することの喜びを実感し、グローバル社会への関心を高めていきます。

絵巻物に描かれた当時の様子を読みとる